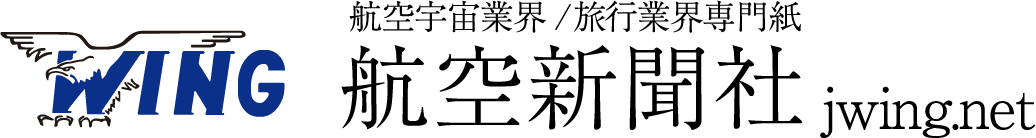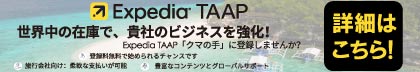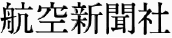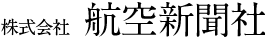WING
新技術で加速する宇宙開発

現地で物資を開発・製造する試みスタート
近年、3Dプリンターなど先進技術を活用して、宇宙空間で宇宙開発に必要な物資を開発・製造する試みに注目が集まっている。地上からロケットで打ち上げる場合、一回あたりに運べる大きさや量が制限される。地球周回軌道上などに拠点を設けて現地で造れるようになれば、これまで運べなかったものも利用できるようになり、宇宙開発の革新につながると期待される。「こうした取り組みは米国などが先んじて進めているものの、覇権は今のところいない」(文部科学省研究開発局 宇宙開発利用課課長補佐 池田宗太郎氏)といい、日本政府も文部科学省を中心に補助金による支援を用意するなど積極投資する構えだ。
近年、安全保障などの観点から宇宙開発が世界的に加速しており、2040年の市場規模は15年比で約3倍の150兆円になると予想される。それにともない、例えば人工衛星の運用や宇宙飛行士の滞在に要する物資など、さまざまなものを宇宙空間に持ち出す必要が出てくると考えられる。
ただ、現状ロケットに積める大きさや量には限りがあるうえ、打ち上げるためのコストも大きい。そこで、3Dプリンティング技術などを用いて宇宙でものを造ることで、これまで持ち込みが難しかったさまざまな物資を利活用できるようにし、宇宙開発を大幅に進化させる取り組みが萌芽しつつある。
池田氏は「宇宙船の中で造る・外で造るの2種類がある」と説明する。前者は、宇宙ステーションの内部で金属部品などを製造することにより、「宇宙機の現地製造やオンサイトメンテナンスを可能にする」ようなケース、後者は、「ロケットに積むためには、折りたたむなど手間の掛かる大型のアンテナを製造する」ようなケースが想定されるという。
欧米では政府を巻き込んだ研究開発がすでに始まっている。オーストリアのベンチャー企業、Incusは欧州宇宙機関(ESA)支援のもと、月面のスクラップメタル(以前の月面ミッションや古い衛星など)を金属3Dプリンティング技術を用いて再利用する技術を開発中。月面のレゴリスを用いた3Dプリンティング技術の実証も進めている。
米航空宇宙局(NASA)などが支援する米ベンチャーのOrbital Compositesは、地上向けの汎用的な3Dプリンティング技術を含めた製造やロボティクス技術をコアに、軌道上でキロメートル級の巨大アンテナを製造する技術開発に取り組む。官民一体となって新領域の開拓を推進することで、次世代の柱となる技術をいち早く手に入れる算段だ。
こうした流れに乗るべく、日本も立ち上がった。政府は新設した「宇宙戦略基金」を基に今後10年で1兆円規模の宇宙開発投資を行うことを決めており、軌道上製造・組立技術の開発を含む軌道上サービスに向けても、文科省を主体に165億円を支援する方針を打ち出している。4~7件を採択する計画で、支援機関は最長5年間とする。6月下旬から
池田氏は宇宙での開発・製造について、「日本の強みを生かせる分野である一方で、現時点ではプレイヤーがほとんどいない。産業として成立するのもまだ先だ」と現状を分析する。そのうえで、「黎明期の今はチャンスだ。参入する場合、地上で活用できる技術を開発して収益を得ながら、宇宙に適応できる技術も作り出していくという視点を持ってほしい」とし、多様な企業の参入に期待を寄せた。
※写真=日本AM学会セミナーで講演する池田氏
https://jwing.net/w-daily/pict2025/2505/0526ikeda-w.jpg