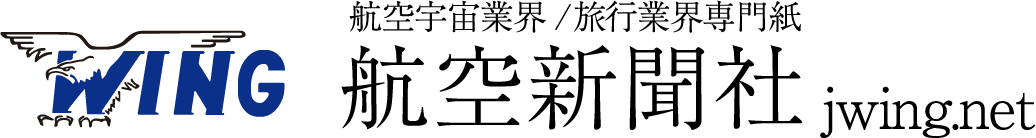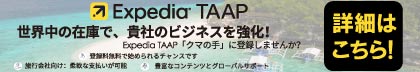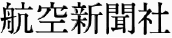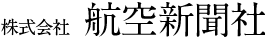WING
大船渡市の大規模林野火災が残した教訓

大規模林野火災に対応できる航空体制とは?
総務省消防庁は、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 報告書をまとめた。この火災は、今年2月26日に大船渡市赤崎町内で発生した林野火災で、火災発生までの記録的な少雨、発生日前後の乾燥、強風、地形など、複合的な要因が重なって急激に拡大。火災を覚知してから、わずか2時間ほどで延焼範囲が600ha以上に達し、最終的には約3370haを焼き、1964年以降、最大の林野火災となったもの。
この林野火災を覚知し、延焼範囲が拡大すると、岩手県知事は消防庁長官に対して緊急消防援助隊の応援を要請。直ちに緊急消防援助隊が出動した。
林野火災としては最大規模の15都道県から緊急消防援助隊が駆け付け、岩手県内応援部隊、地元の消防本部及び消防団が一日あたり最大約2100 名体制で、昼夜を問わず消火活動に従事した。
火の手が市街地に迫りつつあるなか、陸上における消火活動では、市街地への延焼阻止を主眼に、住家付近に延焼阻止線を設定。予防散水や消火活動を展開したほか、林野内に入っての消火活動を実施した。さらに、航空部隊も投入。空中からの消火活動では、延焼阻止及び消火に向け、自衛隊と連携してヘリコプターによる散水を実施した。地元・大船渡市消防団は、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した消火や残火の処理、夜間の見回り、被害状況の情報収集などの活動に従事した。
※画像=今年2月に発生した大船渡市の大規模林野火災(出典:大船渡市資料より)