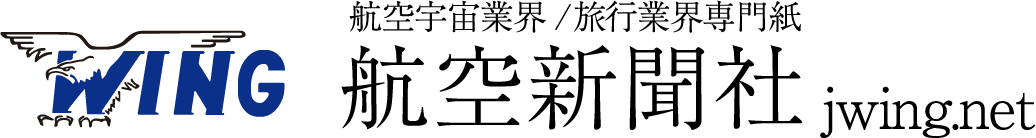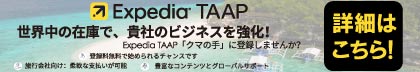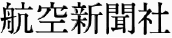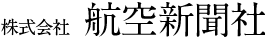WING
ISC畑田社長に聞く成長戦略

ロケット開発・他社支援・宇宙ビジネス共創の3事業に力
近年、安全保障需要の高まりなどを背景とした宇宙産業の急速な成長に伴い、民間企業を主体としたロケットの開発が世界的に盛り上がっている。とくに、最大手である米スペースXの大型ロケット「ファルコン9」が、第一段を再使用可能にしたことで打ち上げコストを大幅に下げたことはインパクトが大きく、業界を刺激した。日本でもロケット開発のスタートアップが続々と登場しており、各社多様な戦略で開発に挑んでいる。今回、世界に先駆けて再使用可能な小型ロケットの実用化を目指す将来宇宙輸送システム(ISC、東京都中央区)の畑田康二郎社長に、足元の取り組みや成長戦略について聞いた。
――宇宙ビジネスを始めたきっかけは。
「大学院を卒業してからずっと経済産業省に勤めていて、宇宙産業の活性化にも携わった。10年ほど前に宇宙政策を担当した頃はまだ宇宙ベンチャーも少なく、裾野を広げなくてはという思いがあった。行政側で産業創成に取り組むうち、宇宙産業の将来性や重要性をより強く認識するようになり、22年にISCを自ら立ち上げるにいたった」
――足元で注力していることを教えてください。
「中期的な目標として、28年3月末までに北海道大樹町にある商業宇宙港『北海道スペースポート(HOSPO)』にて、再使用ロケットによる小型人工衛星の打ち上げ実証を行う計画だ。そこに向け、最近では液体メタンエンジンの燃焼試験や機体の落下試験を実施したほか、HOSPOを運営するSPACE COTAN(スペースコタン、北海道大樹町)と、射場開発および射場利用に係る基本合意書(MOU)を締結するなど準備を進めている。福島県の補助金事業にも採択された」
「当然、人工衛星の運搬や有人宇宙飛行など自社のロケットを使ったビジネスが最終的な柱になる想定だが、稼げるようになるまでに時間が掛かる。そのため、他に2つのビジネスモデルを考えている。1つは、ロケットの開発や管理などに必要なプロセスを支援するプラットフォームの提供だ。今は、例えば軌道計算など複雑な作業を行うために、手間と時間をかけて自社でソフトウェアを開発するケースが多い。ISCではそうしたノウハウを先行して蓄積しているため、プラットフォーム化して有償で提供することができると考えている。すでに数社に声掛けをしており、今年中に事業化に向けた検証を行いたい。もう1つは、宇宙ビジネス共創事業で、これも今年中に売上が発生する想定。これまで培ってきた宇宙分野の知見を生かし、参入を検討している企業などに助言や必要に応じた支援を行うことで、事業化を手伝えるような取り組みも推進する」
――ISCが開発するロケットの強みは。
「小型衛星などを運搬する際、低コストでチャーターできる点が強みだ。現状、大型ロケットのライドシェアを利用すれば100kgの人工衛星を1億円程度と低コストで輸送できるものの、主衛星の打ち上げに合わせる必要があるため、スケジュールの融通が利かない。目的地も選べないため、投入された場所から燃料を消費して自力で移動する必要がある。また、既存の使い捨て小型ロケットをチャーターする場合、一般的に10億円程度費用が掛かってしまうため、ベンチャーなどは手を出しにくい。ISCが開発するのはまだ市場に普及していない小型かつ再使用可能なロケットで、1回あたりの費用を抑えられる。1回の使用料を5億円程度にしても、利益が出るコスト構造を目標にしている」
複数エンジン並行開発で選択肢拡大
ハイブリッド・再使用など先端技術開発推進
――エンジンの開発にも力を入れています。
「自社開発の高性能液体燃料エンジンのほか、Letara(レタラ、札幌市西区)や米Ursa Major(ウルサメジャー)と協業して、計3種の異なるロケットエンジンを開発中だ。レタラと組んで開発しているものは液体と固体を組み合わせたハイブリッドエンジンで、安全性が高く有人宇宙飛行に用いる場合などに適している。ウルサメジャーと取り組んでいるものは、再使用可能な液体燃料エンジンで、機体同様何度も使えるため1回あたりのコストを抑えられる。性能・安全・コストなどさまざまな強みを持ったエンジンを並行して開発することで、必要に応じて最適なものを選択できるようにする」
「ハイブリッドエンジンは世界的に黎明期の技術で、オーストラリアや韓国、台湾、ドイツなどで研究が盛んだ。ISCでは、28年くらいまでに人工衛星100キログラム程度を打ち上げられる能力を持ったものを開発したいと考えている。再使用可能エンジンについては、開発の主体が米国なので、非常に厳しい試験をクリアしなければならない。ただ、米国で開発を行った経験が、日本で戦っていくうえで必ず強みになるので、粛々と進めていきたい」
大樹町以外に複数射場検討
南相馬など候補、洋上や内陸も視野
――中長期的な目標について。
「28年以降は、日本で年100回人工衛星などを打ち上げできる体制を最終目標に、段階的に整えていく。再使用型であれば、おおよそ7台のロケットがあれば100回の打ち上げも可能だと試算している。また、高頻度に打ち上げるためには、気象条件やアクシデントに左右されないよう大樹町だけでなく複数の打ち上げ場所を確保する必要があるため、準備を進めていく。大樹町以外の発射場で最有力候補になるのが、すでに拠点を置く南相馬市だ。地理的に南側には打ちにくいものの、東側は太平洋に面して開けているため条件が良い。大きな港もあるため、洋上に発射場を作って南側に飛ばせるようにすることも考えられる。このほか、場合によっては内陸側も視野に、発射場の候補を選定していく」
「32年以降には、有人飛行が出来るようにする計画だ。宇宙をより身近なものにするのがISCの使命だと考えており、そのためにも宇宙旅行など、人を乗せて飛ぶというところにとくにこだわっていく。ハワイ旅行に行くような感覚で宇宙に行けるようにしたい。そのためにもまずは、無人飛行で実績をしっかりと積み、安全性を証明していく」
※写真=インタビューを受ける畑田社長
https://jwing.net/w-daily/pict2025/2507/0703isc-w.jpg