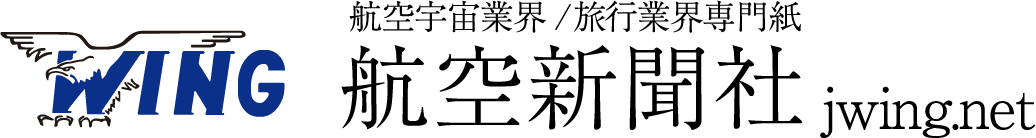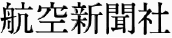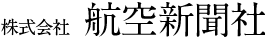ウイングトラベル
★ANAHD、新予約システムで株主優待割配席増へ

来年5月19日までは「一旦、空席待ちを」
ANAホールディングスの定時株主総会が6月27日に都内で開かれた。このなかで株主還元のあり方を問う質問が相次ぎ、とりわけ株主優待割引を使った航空券の予約が取りにくいことへの指摘が飛んだ。これに対してANAホールディングスは「来年5月19日以降、新たな国内線の予約サービスシステムに移行する」とし、「この新たなシステムでは、今までよりも格段に株主優待割引に対する配席を増やす」計画にあることを明らかにした。
新システム移行前の来年5月18日までの間は、既存の予約システムにおける改善を進める。
「大変申し訳ないが、現在の予約システム上、株主優待の座席の開け閉めが非常に難しい。運賃に従って自動的に株主優待の座席の分析が閉まってしまうシステムになっている」とのこと。そのため株主優待割引が使いづらい状態が生まれているとした。
対策として「(株主は)一旦、空席待ちをつけていただきたい」と呼びかけ、「毎日、どれだけ株主優待のお客様の空席待ちがあるのか確認して回答する」体制を構築。さらに、「現在のシステムに可及的速やかに、夜間に株主優待のお客様の空席待ちに回答していくシステムの改修を加える」計画にあるとのことだ。
株主が不満を募らせている背景には、株主優待割引が使いづらい一方、年に複数回、株主優待よりも割安なタイムセールが実施されていることも理由の一つだろう。
ANAはこのタイムセールの実施について「コロナ後、かなり国内線のお客様の数に戻ってきてはいるものの、ビジネスのお客様の需要がまだ7割程度しか戻ってきていない。従って国内線の収益性を高めていく観点では、ビジネス以外のレジャーのお客様にいかに需要を喚起していくのかという点が非常に重要」であると説明して理解を求めた。
「このタイムセールをご利用されているお客様の数は、当年度で前年の141%に達しており、非常に多くのお客様にこのセール運賃をご利用いただいている」とのこと。セールを実施したとしても、全体の国内線平均単価は前年度比で101%の水準を維持しており、ANAとしては精緻なイールドマネジメントによって、旅客数増、平均単価の引き上げに成功していることを明かした。旅客数が増加することで株主優待割引がさらに使いづらい状況となっているが、ANAとしては今後、システム改修などを通じて、より使いやすい株主優待割引のあり方を模索していく考え。
※画像=芝田社長は株主に株価向上、株主還元の更なる強化を約束した
過去最高売上も伸び悩む株価
芝田社長、自社株買い・中間配当制度導入も
ANAホールディングスは、2024年度業績で過去最高の売上高2兆2618億円を記録し、営業利益も2月に上方修正した見通しをさらに166億円上回る1966億円で着地した。コロナが収束し、業績は着実に成長軌道へと再び乗っているが、一方でそれでも株価が伸び悩みをみせていることも事実だ。
株主からは株価伸び悩みへの指摘も相次ぎ、ANAホールディングスの芝田浩二社長は「株価は、私共も日頃から留意をしている」とコメント。その上で株価の伸び悩み要因について「コロナ禍に実施した公募増資の結果、発行済み株式数が増えていることが1つ。もう一つは株主還元が十分ではないという点などあろうかと想定している」との見解を示した。
芝田社長は「社内で現在議論中の次期中期経営戦略では、株主還元の強化を打ち出していきたい」と述べつつ、「当期の配当水準は決して十分なものではないと考えており、更なる事業の成長を通じて一層の配当水準の引き上げを早期に実現する」として、今期60円の配当からの更なる引き上げを目指すとした。
その上で「社債型種類株式を発行した際の資金使途として、自社株買いも選択肢の一つとなるほか、中間配当制度の導入も検討していく」ことを明かし、株価上昇・株主還元の強化に取り組む考えを明かした。
ANA井上社長が明かす成長原動力の3つの柱は
株価の伸び悩みが課題となるなか、ANAホールディングスの中核事業会社である全日本空輸(ANA)の井上慎一社長は今後、如何に成長を描き厳しい競争環境を勝っていくのかに言及。「競争優位性を保つためには事業規模が大きいことが必要だ。小さいと勝てない」ことを強調し、「日本のエアラインは、日本の人口が縮小するなかで、勝つためには国際線への進出が必要だ」とし、ANAが羽田空港で最大の国際線発着枠数を有していると説明。アジア、北米、欧州線を含め、羽田空港で本邦最大のネットワークを有していることに触れた。
「この最大の事業を活用し、日本離発着のビジネス需要、訪日需要をしっかり取り込むと同時に、日本を経由したアジアと北米の流動もしっかり取り組むことに成功しており、これは昨年度の業績に繋がっている」との認識を示し、「この優位性は今年度も継続している。収益を生み出す大きなエンジンとなっている」とした。
また、他エアラインとの共同事業(ジョイントベンチャー:JV)も、成長の原動力の大きな柱であることを強調。「ANAの国際線の旅客の売上は海外販売比率が約6割になっている。日本ではなくて海外マーケットで売れている」ことを明かした。
ANAは米国のユナイテッド航空、欧州のルフトハンザドイツ航空とJV事業を展開し、今年4月からシンガポール航空とのJV事業をスタート。シンガポール航空とのJV事業により、「インド、東南アジア、オセアニア、この地域でも、非日系のお客様に対する販売力の強化を推進していく」方針で、「3つのJV事業で、世界の要請となるエリアを全てカバーするグローバルな提携体制が完成したという風にご理解いただきたい。この強みに関しまして、他社が容易に追随できないエアラインを目指す」との考えを明かした。
さらに、コロナ禍で旅客事業の収益が厳しかった時に下支えした貨物事業についても柱の一つであると説明。「コロナ後の事業環境が大きく変動する中でも、世界的なサプライチェーンの変動や地政学リスクに対応し、eコマース市場の拡大のチャンスなど、的確に捉え、高付加価値の貨物から緊急貨物の取り込みに成功している」とし、「現在、現在調整中の日本貨物航空との統合が成立すると、他社にはない大型貨物専用機がラインナップに加わる。これを活用して、より強固なカウントネットワークを世界中にこう構築していく」との戦略を明らかにした。
エアージャパン、ピーチと統合は「一切ない」
また、株主からエアージャパンの年間平均搭乗率が69.3%に留まったことを憂い、ピーチ・アビエーションと統合すべきとの指摘もあったが、これに対して芝田社長は「3つのブランドでマーケットをしっかりと取っていく。現在、エアージャパンとピーチ・アビエーションを統合するという計画は一切ない」と回答した。
エアージャパン峯口秀喜社長は昨年度の平均搭乗率について「当初は80%という目標を立てていたが、残念ながら昨年度については低い数字をとなった」ことに触れつつ、上期の欠航が大きく影響したとした。その上で、「下期の平均搭乗率は83%。下期は海外のお客様に非常に乗っていただき好調だった」とコメント。「2年目を迎え、収益性をしっかり改善していく」と話した。
787、日々の点検・整備を確実に
737MAXは品質担当者が現地駐在
また、事前質問ではエア・インディアの787型機がア去る6月12日に墜落したことへの不安の声も多数寄せられた。これはANAグループにおいて、計88機もの787型機を運航しているため。
ANAホールディングスは「現時点で事故原因は特定されておらず、特別な対応に関する指示もない」としながらも、「ANAとしては日々の点検、整備を確実に実施するとともに、原因究明の情報把握に務め、必要な対応をタイムリーに行っていく」とした。さらに、ANAが787型機のローンチカスタマーとして同機の開発段階から携わっていることに触れ、「安全性、信頼性向上に向けて独自の整備プログラムの設定や改修を促進してきた。として、引き続き、安全安心な空の旅を旅客に提供するとした。
加えて、今後導入する737-8型機についても、「昨年秋からANAの品質担当者を現地に駐在させ、ボーイングの品質改善の取り組みを直接確認している」と説明。「ANAの検査員が、当社機1機1機の製造工程において品質の作り込みが行われていることを確認していく」方針にあることを明らかにした。