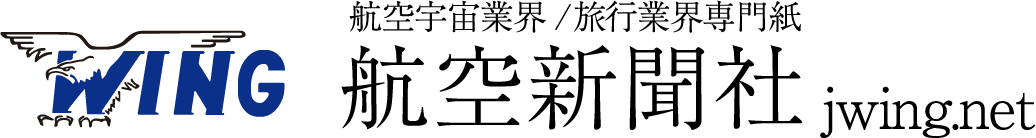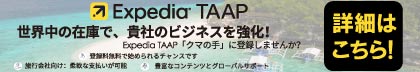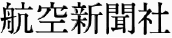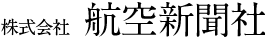ウイングトラベル特集
【潮流】長期的視野の司令塔づくり

今年の訪日外客数が9月の時点で3000万人を突破した。単月ベースで見ても20カ月連続で過去最高を更新。このままの流れで推移していけば4000万人の大台突破が現実味を帯びてきた。コロナ禍による観光需要の消失という未曽有の危機を経て、2016年に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」において、2020年の達成目標として掲げた4000万人という数字を5年遅れで実現することとなりそうだ。
観光庁の村田茂樹長官は「訪日インバウンドはさまざまな要因に左右される」として、4000万人達成の見通しについて直接的な言及は避けるものの、「訪日インバウンドについては、引き続き力強い成長軌道を描いている」と評価した。そして「戦略的な訪日プロモーションと地方誘客を積極的に進めて行き、この流れを継続させていきたい」と意気込みを示した。
わが国の観光を成長させていくための大前提として、村田長官は「持続可能な観光の実現」を挙げる。これを実現するためには「国民生活との両立が不可欠である」と指摘するとともに、「必要な政策と予算の確保に向けてしっかりと取り組んでいく」と強調した。
では、持続可能な観光の実現に求められるものとは何か。まず、さまざまな関係者が一枚岩となり、課題解決に取り組むことであろう。しかし、足並みをそろえるためには時間を要する。そのために全体を統率する「司令塔」の存在が欠かせない。
その第一義的な役割を担うのが、観光庁ということになる。日本観光振興協会(日観振)が、最近取りまとめた提言の中で、「観光庁は国全体の観光戦略を統括する司令塔として強いリーダーシップを発揮し、観光政策を戦略的かつ体系的に推進することが求められる」と指摘していたが、まずは政府全体が一つの方向に向かって一丸となる体制を築くことが重要であり、その基盤を固める必要がある。
その基盤整備の要となるのが、現在策定に向けて議論が進む「第5次観光立国推進基本計画」だ。新たな計画が、わが国観光の成長軌道をさらに上向かせるものとなることを願わずにはいられない。
2026年度から始動する観光立国推進基本計画では、明日の日本を支える観光ビジョンで掲げた2030年の訪日外客6000万人、消費額15兆円という目標の実現を図るとともに、わが国観光全体の底上げを目指す基本方針を掲げることになるが、その道のりは決して平坦ではないだろう。
せとうち観光推進機構の真鍋精志会長は「訪日6000万人時代に向かう中で、観光をめぐる課題は一層複雑化するのではないか」と指摘する。2030年を明るく迎えられるかどうかは、これから顕在化する新たな課題にどう向き合うかにかかっている。
せとうち観光推進機構をはじめ、全国10の広域連携DMOは、このほど観光庁に対して安定的な財政と人材確保。そして、観光関連データの整備に向けてさらなる支援拡大を求める要望書を提出した。
広域連携DMOは、地域が持つ多様な観光資源を繋ぎあわせて新たな人流・商流を生み出す観光地経営を担うことが求められている。しかし、現状ではその基盤が十分に整っているとは言い難い。
せとうち観光推進機構の真鍋会長は「事業計画が単年度ベースとなっていること。そして、DMOを担う人材が短期間に入れ替わってしまうことが課題だ。地域の観光産業の司令塔としての役割を果たすには、基盤の強化が不可欠である」と強調した。
持続可能な観光の実現を成長の前提とするならば、息の長い活動を可能にする環境整備こそが重要だ。
地域が検討を重ねて立ち上げた計画を実行に移す段階で、担い手の交代や財政見直しが頻発すれば、前進が阻まれてしまうことになりかねない。
今後、状況が複雑化していくことを見据えれば、川上から川下まで一貫した長期的な視点で政策を実現できる体制を築くことが欠かすことができない。
立場の違いによる足並みの乱れを防ぎ、国・自治体・地域が同じ方向を見据えて行動することが、真の意味での「持続可能な観光立国」への道なのではないだろうか。(嶺井)