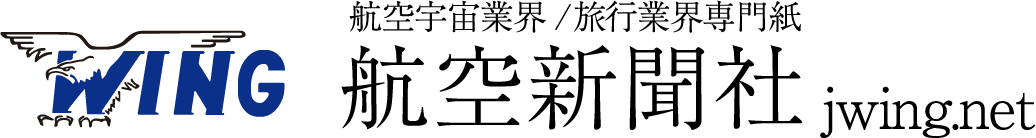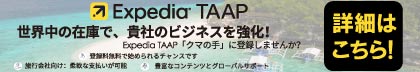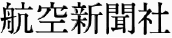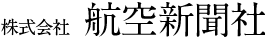【潮流】観光“現在地”の捉え方
10月21日に高市早苗内閣が発足し、国を取り巻く動きも新たな一歩を踏み出し始めた。観光政策の舵取りを担う国土交通大臣には、金子恭之氏が就任。自民党出身者として16年ぶり国土交通行政のトップを担うこととなった。
金子国交大臣は就任にあたり、観光に関連する内容として高市首相から「観光振興を通じた地域の活性化とオーバーツーリズム対策に関する指示を受けた」ことを明かした。
さらに金子大臣は「観光立国の実現には、観光がもたらす恩恵や観光振興の意義を国民が理解することが重要である」と指摘。観光を含めた国土交通行政全体を見据える中で「できるだけ現場に足を運び、関係者の声に耳を傾ける」と述べ、現場主義を胸に職務にあたっていく考えを示した。
新内閣から発せられた言葉を借りれば、政府は「観光で地域をさらに活性化させること。そして、オーバーツーリズム問題が起こらないようにすること」という課題があるということを観光を取り巻く「現在地」として捉えていると位置づけることができるのではないかと考える。
では、観光に携わる事業者はどのように捉えているか。星野リゾートの星野佳路代表は「訪日インバウンドに関してバブル期という指摘をする声があるが、訪問客数の増加にあわせて、顧客満足度の低下が見え始めている。この傾向が進めば、3~5年後には実数の減少につながる」と警鐘を鳴らした。星野代表は、今後適切な対策を講じなければ、まさに「バブル崩壊」が起こり得る局面にあるという「現在地」を指摘する。
一方で、日本人の海外旅行をビジネスの中核に据えている事業者が「現在地」をどのように捉えているか。その答えは「未だにコロナ禍を脱することができていない」ということになるのだろう。
日本政府観光局(JNTO)の発表によると、9月の出国日本人数は前年同月比15.0%増の139万4500人となり、5月から5カ月連続で100万人台を突破する結果となった。また、1~9月の累計を見ると1085万7200人となり、1000万人のラインは突破したものの、コロナ禍前の2019年の1506万2543人と比べる72%の水準にとどまっている。旅行に対する意欲は強いものの、実際の渡航に結び付いていない状況が続いている。
高市首相の就任で証券市場は「高市トレード」として、過去最高値の更新が見えてきているものの、海外旅行需要喚起の起爆剤となり得る為替はいまだに1ドル150円台で推移しているし、物価上昇も高止まりしたままだ。ただ、この状況を受け止めながら、成長軌道を描くことを考えていかなくてはならない局面に立たされているのが実情だ。
足元の状況を見ると、旅行会社や航空会社、空港事業者などは、パスポート取得費用の支援や若年層に海外旅行に対する関心を持たせるキャンペーンの展開など旅行機運の醸成を図るための取り組みが行われているのに加え、従来とは異なる旅客層を獲得しようとする施策に打って出るなど、「あの手この手の」工夫を行っているところだ。
そうした中で、観光に携わる関係者はそれぞれの立場に基づいて「現在地」を確認した上で、今後の展望を描いていくことが求められている。
観光の恩恵という部分で捉えるならば、全国の津々浦々の地域が観光で賑わいを見せているとは言い切れない。また、日本人の旅行者は、世界の観光の魅力にもまだまだ触れきれていないのではないだろうか。まだまだ上向くポテンシャルがある中で、顧客満足度の低下が見え始めてしまっているようでは、将来を見据えることはできないのだろう。
ここに来て「オーバーツーリズム」という言葉がキーワードとしてよく聞かれるようにはなっているが、目線を変えると、日本の場合は未然に防ぐという手立て打つことができる「猶予」があると言えるのではないのだろうか。
旅行者と地域住民が共存できる環境整備は、日本ならではの視座から構想できるはずだ。こうした取り組みを契機として、世界とのつながりをさらに広げる可能性も開ける。今のうちに好循環を築いていくことができれば、観光立国としての地位確立に近づくことになる。そのためにも今立たされている「現在地」を見誤ることがあってはならない。(嶺井)