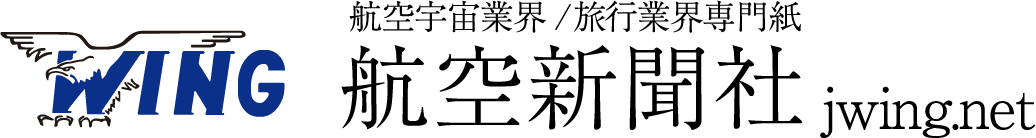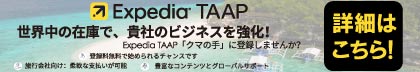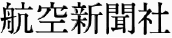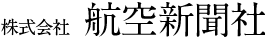【潮流】「夢洲」の地で何を感じたか
本号の発行日である10月13日に大阪・関西万博が閉幕する。開幕からの累計来場者数は2500万人を突破し、約2200万人となった2005年の「愛・地球博(愛知万博)」を上回る見込みだ。
以前の小欄でも触れたが、今回の万博は、開幕当初は盛り上がりを欠いたものの、会期を重ねるごとに来場者数は増加の一途を辿り、主催者の想定どおりの展開となった。
筆者はゴールデンウィーク直前の4月末に万博会場を訪れた。そのときに撮影した写真や動画を、最近の会場の光景と見比べてみたが、熱気と活気の高まりを一目で感じ取ることができた。
この結果を下支えした要因として、やはりSNSの存在を無視することができない。万博開催の是非をめぐってさまざまな意見が交わされる一方で、会場の状況をリアルタイムで把握できたこと、さらに国内外のパビリオンでの体験や人々との触れ合いがネット上を通じて共有されたことも大きい。
さて、本紙の紙面から大阪・関西万博に関して振り返らせてもらうと、最も多く報じることとなったのが、出展した世界各国・地域ごとに設定された「ナショナルデー」に合わせて来日した観光関係者によるセミナーやレセプションの模様。そして観光行政や観光局幹部によるインタビュー記事であった。
各国の関係者が口を揃えるように、本紙の取材に対して語ったのが「万博で多くの人々に、わが国のことを知ってもらうことができた。この流れを観光誘致につなげたい」というものだ。
万博を訪問した人に話を聞くと、主要国より、これまであまり知ることのなかった中央アジアやアフリカなどの国や地域のパビリオンが印象に残ったという声を耳にする機会が多かったように感じた。
知られざる世界の魅力を伝える契機となった大阪・関西万博。ここで築かれたムードが出展者の思惑通りに進むかどうかが注目されるところだが、現実は厳しい。
政治・経済を取り巻く状況は国内外ともに依然として混迷しており、物価高の状況がすぐに改善するとは言い難いのが実情だ。
われわれが万博会場で取材した各種イベントには、多くの旅行・観光関係者が姿を見せていた。経済情勢の改善が見通せない中で、万博が日本人の海外旅行需要をどこまで喚起したのか。その答えは、これから市場に登場する旅行商品や消費者の動向に表れるだろう。これからの行方を注視していきたい。
大阪・関西万博を訪問した人は世界への関心だけでなく、色々な発見をしたのではないだろうか。
筆者が発見したものの1つとして大阪・関西エリアの観光における魅力と利便性の高さを挙げたい。
万博会場には、バスと地下鉄を利用して訪れたが、その際に使用したのが「KANSAI MaaS」のアプリだ。万博訪問に際して役立ったのはもちろんなのだが、アプリから定期的に通知される情報について興味を惹かれた。
特に印象的だったのが、関西エリアの観光スポットを訪問するのにあたって便利な企画切符が用意されていること。そしてこれまで知らなかった地域の観光資源を新たに知るきっかけになったことだ。
関西と言えば、どうしても京都市内の観光客の集中に目が行きがちになるが、京都以外の地域に観光客を分散させる余地は十分にあると感じた。
KANSAI MaaSアプリを通して、同様の印象を抱いた人も多いはずであり、気づきを促したことも万博がもたらした効果のひとつと言えるだろう。
万博に限らず、国際的なイベントの終了後には「レガシー」に注目が集まる。万博会場の跡地をどのように活用していくのか。あわせて、会場近隣で2030年秋の開業が予定されているIR(統合型リゾート)の動きにも関心が集まることになるだろう。
4月から半年にわたって大阪・関西万博で盛り上がりを見せた「夢洲」の地で、旅行・観光関係者は何を感じ、将来の成長に向けて何を思ったのか。今後の業界動向の中から、その答えを見極めていきたい。(嶺井)