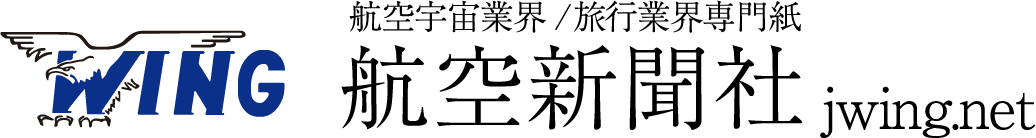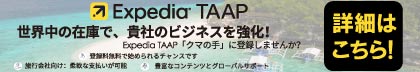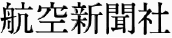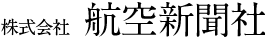WING
シーグライダーのリージェント、防衛部門設立

輸送やMEDEVAC、ISRなど対応
シーグライダーの開発を進めているリージェントクラフト(REAGENT Craft、
リージェント)が7月16日(米デトロイト現地時間)、海洋安全保障需要に対応するため、REGENT Defense(リージェント・ディフェンス)を設立したことを発表した。
ロードアイランド州にある本社において、リージェント・ディフェンス向けの機体開発にも取り組み、中国の海洋進出が著しいインド太平洋地域を中心に、米国とその同盟国を支援するとした。
リージェントのシーグライダーは、民間機として日本航空(JAL)が注目。2023年には社会実装を目指し、包括協定を締結したことは記憶に新しい。
そのリージェントのシーグライダーは、地面効果と水中翼を組合せた機体だ。航空機の高度が主翼幅の半分程度になると、翼端渦の発生が抑えられ、誘導抗力が小さくなる。これにより迎え角が大きくなって揚力が増す現象が、いわゆる地面効果だ。その現象を利用した地面効果翼機は、翼によって揚力を得つつ、地表や水面から数十センチ~数メートルほど浮き上がって、滑るように飛行(航行)する機体、もしくは船だ。
もともと第二次大戦以前にスカンジナビアで誕生した技術だが、1960年代になると、旧ソ連時代にソ連軍が活用。さらにドイツ、そして日本でも研究開発が進んだ。
日本国内では川崎重工業が「KAG-3」を開発。90年代に三菱重工業と鳥取大学がレジャー用に「μsky-1」と「μsky-2」を共同開発し、その後も研究機関(現・海上技術安全研究所)などで研究開発が進むなど、地面翼効果機の技術を蓄積している。
そうしたなかリージェントの機体は、独自の水中翼式地面効果翼を使った設計を特徴とし、軍のミッションにも対応する。水面からわずかに浮き上がって飛行するため、水中のソナー、あるいは空中のレーダーの探知範囲外を飛行することができるとのこと。優れた機動力、低探知特性の設計により、多様な海上防衛ミッションに対応することが可能だ。例えば、兵員・物資輸送、医療搬送(MEDEVAC)および捜索救助、情報収集・監視・偵察(ISR)、さらにはシーグライダーから無人システムの展開など、様々な用途で活用することが見込まれるところだ。
全電動やハイブリッド機を開発
小形無人「Squire」も製品群に
そうしたなかリージェント・ディフェンスは、民間向けの全電動式有人Viceroyの防衛バージョンを開発していくことに加え、完全自律型Viceroy、ハイブリッドモデル、そして1/4スケールの自律ハイブリッドモデル「Squire」など、安全保障用途向けの機体開発に着手することを明らかにした。
このうち全電動の「Viceroy」は、積載量が3500ポンド(約1540kg)、最大160海里(約180マイル)を航行することができる。ハイブリッドモデルは最大1400海里(約1600マイル)の航続距離を誇り、最高160ノット(約180mph)の速度で航行可能な機体とする。そして自律ハイブリッド「Squire」 は、積載量50ポンド(約23kg)で、最大70ノット(約80mph)の速度で100海里(約115マイル)以上を航行可能な機体とする方針だ。
なお、リージェントによれば、分散型海上作戦への戦略的転換を継続的に推進する米海兵隊が同社の開発パートナーであると説明。今年3月には海兵隊戦闘研究所との間で1000万ドル規模の協力締結に踏み切った。さらに米国特殊作戦軍(USSOCOM)および米国沿岸警備隊研究開発センターとの間でも、開発協力を正式に締結したことも明かした。
リージェントの共同創業者兼最高経営責任者(CEO)のビリー・サルハイマー氏は「当社はデュアルユース企業となることを誇りに思う」とディフェンス部門の設立を喜んだ。その上で、「この事業を通して、米国の戦闘員、同盟国に戦略的優位性をもたらす。緊急に必要とされる機動ソリューションを提供する」とした。さらに、「これらの機体を国内で建造することで、米国の製造業の活性化に貢献し、ハイテク関連の雇用を創出する。世界における米国の競争力を回復させる」と、トランプ政権の政策に合致した施策であることも強調した。
※画像=リージェントが防衛部門を設立。米国・同盟国などの海洋安全保障に寄与する(提供:リージェント)