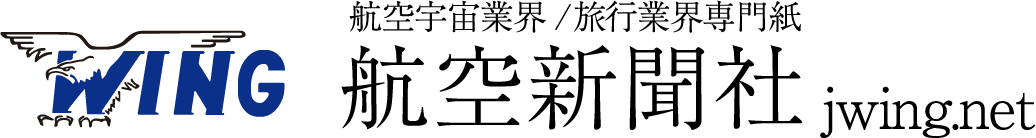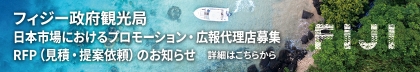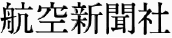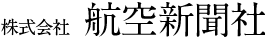ウイングトラベル特集
【潮流】日本流サステナブルMICEとは何か

観光戦略を構築する上で、MICEは極めて重要な役割を担う。企業会議、報奨旅行、国際会議、展示会といったMICEは、多数の人々の移動を伴い、開催地に消費・雇用・知的交流を生み出す。単なる集客イベントではなく、地域経済と産業振興に波及効果をもたらす存在である。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大は、MICEの前提を根底から揺るがした。対面を避けることが求められ、多人数が集まること自体がリスクと捉えられたなか、MICEは最も大きく発想転換を迫られた観光分野のひとつとなった。グローバル企業の重要会議や国際的な意思決定の場は、止めるわけにはいかない。そこで、オンライン会議システムやハイブリッド型イベントの迅速な導入が進み、遠隔であっても成果を確保するための技術と運営ノウハウが急速に蓄積された。
ただ、コロナ禍の収束が見え始めると、人々は再び「同じ空間に集うこと」の意味を再評価し始めた。言葉の端々、表情の変化、雑談から生まれる気づなどの価値はデジタルには置き換えることができない。リアルMICEの再開は、単なる回帰ではなく、対面の価値を再認識したうえでの再出発であるといえるのだろう。
そうした流れの中で、いま最も重視されているキーワードが「サステナブル=持続可能性」だ。環境負荷を軽減することはもちろん、地域に根ざした文化・多様性・コミュニティを尊重しながらイベントを成立させる視点が求められている。規模拡大や来場者数だけを追う運営はすでに時代遅れとなり、MICEは地域とともに価値を共創するフェーズに入っている。
11月4日に東京都と東京観光財団が開催した「サステナブルMICEショーケース」は、その現在地と方向性を示す場となった。
基調講演で登壇した、グローバル・デスティネーション・サステナビリティ・ムーブメント(GDS-ムーブメント)のガイ・ビッグウッドCEOは、日本には「リサイクル文化や食文化、地域に根ざした美意識など、世界に誇る独自価値がある」と指摘し、その価値は「共創を通じてさらに発展させることができる」と述べた。
ビッグウッド氏の言葉からは、日本は“世界標準を追うだけではない、日本独自のサステナブルMICEモデルをつくり得る素地がある”ということを感じ取ることができた。
一方でビッグウッド氏は、ICCA(国際会議協会)の調査にも触れた。イベントプランナーの92%はサステナビリティを取り入れたいと考えているが、実際に実行できているのは57%にとどまる。この「理想と実践のギャップ」は世界共通の課題であり、逆にいえば、ここを埋めることができるMICEデスティネーションは、競争力を一段高めることができると受け止めることもできる。
ショーケースの会場では、環境配慮素材を活用したブース設営や料理、持続可能性に配慮した楽器を用いた演奏など、具体的な取り組みが示され、いずれも興味深い内容で、「ハードの下地」は着実に整いつつあることを示している。その一方で、その価値を適切に説明し、提案し、使いこなす“ソフトの部分”においては、まだ成長の余地があると感じた。
そうした中で、自治体、DMO、そして旅行会社がさらに存在感を高めていくことが重要だ。自治体やDMOは、サステナビリティに強みを持つ事業者と、MICEイベントを企画・提案する旅行会社を適切に橋渡しする機能を強化する必要がある。また、旅行会社は、企画段階で「持続可能性」を前提に置き、地域の価値を理解し、それを言語化し、提案へと落とし込む力を磨くことが求められるのではないだろうか。
ビッグウッド氏は、変革のために必要な三段階を示した。「害を食い止める」「悪影響を最小化する」「良い影響を生み出す」。このステップは、環境だけでなく、社会、文化、経済に対しても適用される発想であるといえる。
サステナブルMICEは、単に配慮的なイベント運営では終わらない。地域の誇り、文化、関係性を可視化し、共有し、未来につなぐ取り組みである。日本はそのための文化的・社会的土台をすでに持っている。それを運営者・企業・地域で共有し、価値として外に伝えられるかどうかが、これからのMICEデスティネーションとしての日本の競争力を決定づけることになるだろう。(嶺井)