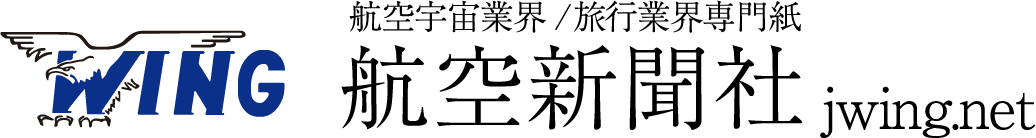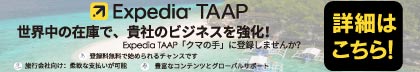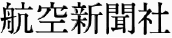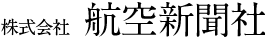旅行会社の強みを発揮できる場に 新体制で迎える2026年のハワイ州観光局【2026年ハワイ州観光局の取り組み ①】

日本からハワイへの旅行需要が堅調に回復するなか、ハワイ州観光局(HTJ)は10月から新たな組織体制での活動をスタートした。新体制のなかでも注目されるのが、日本旅行業協会(JATA)でアウトバウンド促進に努めた稲田正彦氏の日本支局長就任だ。旅行会社の強みを発揮できる場としてのハワイを明確に打ち出し、旅行会社のみならず航空会社、ホテル、アトラクションなど、日本とハワイのパートナーと共に一層の需要拡大を目指す姿勢を鮮明にする。現状を振り返りながら2026年に向けたハワイ州観光局の取り組みについて紹介したい。

ハワイが先頭に立って海外旅行需要を牽引
旅行会社間など、「横の連携」強化目指す
日本支局長就任にあたり、稲田氏は「観光業に携わる人自体が減るなか、旅行会社が元気にならないとマーケットは伸びない。旅行会社がもっとハワイの商品を販売し、旅行会社の存在価値や意義を示す場として、ハワイが先頭に立って牽引し、相互送客に寄与したい」と抱負を語った。
とりわけ重視するのが「横の連携」だ。「旅行会社間の連携、また航空会社やホテル、アトラクション、JATA、観光局などとの協働も図り、業界全体でハワイの需要拡大はもちろん、海外旅行の需要拡大にもつなげていきたい」との考えを示す。
具体的には「既存の現地イベントを旅行会社が共同で集客したり、共同で現地イベントを企画したり、業界が一丸となって集客できる仕組みを検討していきたい」と述べた。
また、「デスティネーションを作る立場としての旅行会社の役割も重要だ」と強調。「コロナ禍を経て、ハワイに行ったことがない旅行会社スタッフが増えている。今一度、教育にも踏み込んで取り組むべきと考えている」と語り、スペシャリスト育成の重要性を訴えた。
今年の日本人訪問者数は71万人と予測
富裕層やシニア層、リピーターが好調に推移

日本からハワイへの渡航者数は、2024年に70万8234人(最終値)を記録、今年は71万人を目指す。今年1~8月の累計は、45万8572人で前年同期比で微増となった。
観光局代表の寺本竜太氏は、「なかでも8月と9月は好調で、特にお盆期間中の8月10日には4219人が入国し、久々に良い数字となり、お盆の時期にしか旅行できない層の需要を確実に取り込めた」とアピールする。
また平均滞在日数は6.4泊に伸長。「初めて訪れる層もリピーターも、より長い滞在を選ぶ傾向にある」という。
こうしたハワイへの旅行需要を支えるのは富裕層やシニア層、リピーターだ。寺本氏は「ファーストクラスやビジネスクラス、プレミアムエコノミーの上級クラスは好調な一方で、エコノミークラスの座席をどう埋めていくのが今後の課題だ」と挙げる。
航空会社で需給調整の動き、供給増に注力
早割利用促進で旅行時期の分散化も推進
航空会社では、上級クラスの単価が上がり、収益が安定化する一方で、ハワイアン航空の福岡―ホノルル線の運休やZIPAIRの成田―ホノルル線の期間運航化など、需給バランスを見据えた調整が続く。
観光局では、引き続き地方発直行便の再開や増便に注力する方針だ。運休や減便の動きがあるなか、日本航空は7月18日より関西―ホノルル線と中部―ホノルル線を共にデイリー運航に増便した。
なかでも中部は9月下旬に開催された「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」が中部初開催となったことから現地で大きな注目を集めた。今後はハワイ島のコナ直行便の再開に向けた取り組みも視野に入れる。
今年の日本―ハワイ間の航空座席に占める日本人比率は7~8月で54%、1~2月と5月で59%、その他の月で60%後半を推移。しかしながら、直近8月は約80%が日本人が占め、お盆の繁忙期以外の分散化も顕著に見られた。
寺本氏は「今後も早割の利用促進を通じて旅行時期の分散化を図り、適正な需給バランスを保っていきたい」と述べ、年間を通じた安定的な需要形成を目指す考えを示した。