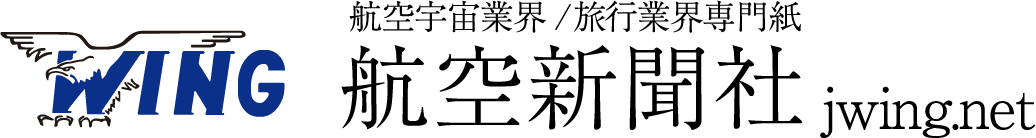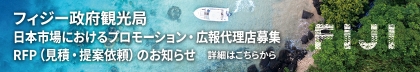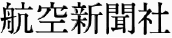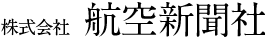ウイングトラベル特集
【潮流】日本人旅行「活性化」への道

観光庁は7月1日付で旅行振興担当参事官を設置する組織改正を発表した。同庁は同日付で村田茂樹長官が就任し、新体制がスタートした。旅行振興担当参事官の設置について観光庁はプレスリリースを発出。新組織への並々ならぬ意気込みを示した格好だ。
新設した旅行振興担当参事官は、これまで観光産業課が担っていた旅行業に関する業務。そして観光人材の確保・育成に関連したもの。国際観光部のアウトバウンド促進、さらに観光地域振興部観光資源課が担当していた国内交流に関する分野を担当することとなる。
今回の組織立ち上げの狙いとして、観光庁はさらなる国内旅行の活性化に向け、日本人の国内旅行を高めていくこと。好調な訪日インバウンドとの相乗効果を生み出し、アウトバウンド需要を喚起していくこと。そして、観光需要の回復等に伴い人手不足感が一層高まる中で観光人材の確保・育成を挙げた。
旅行振興担当参事官が向き合う主要課題について、足元の状況を改めて整理しておきたい。