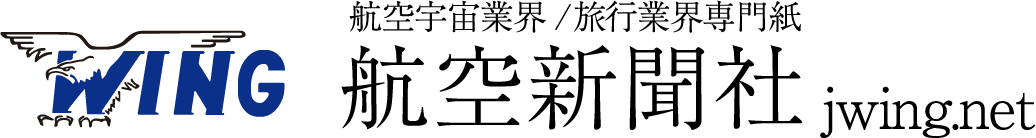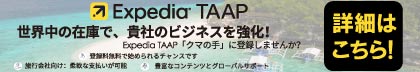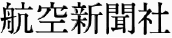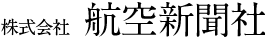ウイングトラベル
★茨城空港将来ビジョン、40年代末に170万人目標

大井川知事、「首都圏第3空港として飛躍可能性の道筋」
茨城県の大井川和彦知事が7月4日、開港15周年を迎えた茨城空港の将来ビジョンを策定したことを明らかにした。同ビジョンのなかで茨城空港が目指すべき姿、果たすべき役割として、茨城県・近隣県の更なる成長や豊かな生活を支える(1)国内外との観光・ビジネスや地域の賑わいの拠点となる空港、首都圏第3空港として(2)日本の国際・国内航空需要に対応する空港、そして首都直下地震などの大規模災害時に(3)茨城県をはじめ周辺県の災害対応の拠点となる空港という3つの柱を掲げた。
茨城県としては、現港利用者数がコロナ禍前の2019年度に年間約78万人だったところ、2040年代末までに170万人の利用を目指していく方針だ。
大川知事は茨城空港について「利便性の向上やインバウンドの需要の急激な増加など、取り巻く状況が大きく変わってきている」と説明。こうした状況を踏まえ、茨城空港が今後目指すべき姿、果たすべき役割、実現するために必要な取組を将来ビジョンとして策定したことを明かした。その上で策定したビジョンについて、「今回のビジョンは、これからの茨城空港が大きく発展するという姿を、具体的に方向性を示せた。これからの茨城空港は、首都圏の羽田、成田に次ぐ第三の空港としての飛躍が可能であるという道筋を示せたことは非常に重要なことではないか」と評価した。
※画像=茨城空港の将来ビジョンが策定。首都圏第3空港として飛躍の道筋を示した
国内線、SKY等に更なる増便働きかけ
国際線はアジア等未就航国展開など視野
前述した3本柱を実現するために、「まず、国内外をつなぐ路線ネットワークの拡大・充実に取り組む。既存路線の増便や新規路線の誘致のため、より積極的に茨城の自然や食、そして、ゴルフなどのプロモーションを実施することにより、さらなる双方向の交流拡大に取り組んでいく」と話し、国内外の路線ネットワークを拡充に取り組むとした。
「国内線でも過去最高の旅客の更新をし続けており、スカイマークが中心になると思うが、福岡に続けて、さらにほかの地域での増便ということも検討いただけるよう、働きかける」と話すなど、スカイマークに国内線の更なる充実・強化を要請していく考えを明かした。さらに、「チャーター便なども含めて、他の国内路線の確保と追加ということも、当然、視野に入れなければいけない」とした。
一方、国際線ネットワークに関しては「現在、中国、韓国、台湾、それぞれ路線があるが、今後、さらに需要を拡大させて、一つの国で複数路線という期待も非常に大きい」ことに言及。まずは1カ国で複数路線の展開を視野に入れつつ、「アジアを中心に、他の国との路線の可能性というのも、今後、探っていきたい」と話し、未就航国とのネットワーク接続を目指す考えに触れた。
旅客やエアラインの利便性向上のための環境整備も進める。大川知事は「空港ターミナルビルの機能強化や、駐車場の容量拡大、増加する空港需要に対する誘導路の増設や駐機場の確保などに取り組み、より使いやすい空港を目指す」考えを明かした。
茨城空港の現・ターミナルビルは、開港時に年間81万人の利用を想定して設計。当初1時間あたり国内・国際それぞれ最大1便の受け入れを前提にターミナルビルを建設したが、2023年10月から受け入れ制限を緩和し、現在は2便以上受け入れている。就航機材についても、国内線は130席クラスを想定して設計したところ、蓋を開けてみれば177席(737型機)クラスの機材が就航しており、ターミナルビルの設計以上の受け入れを行っていることが実情だ。
この結果、例えば出発時には国内・国際線の保安検査レーンは現状1レーンのみで、2便分の旅客を検査しなければならない際には過大な時間を要することに。待合室も298席を設置したが、2便分の旅客ともなれば、最大約360名分の席が必要であり、座席スペースが不足してしまっている。
到着時も手荷物受取場のターンテーブルが1カ所のみとなっており、2便が同時に到着したような場合には過大な待ち時間が発生。当然、狭隘なスペースが大混雑状態に。バス待ちなどの旅客の滞留も発生している状況だ。
茨城県としては今後、1時間に国内・国際線各2便以上の航空機を円滑に受け入れることができるよう、ターミナルビルを拡張し、保安検査場、待合室、手荷物受取所などを増設、自動化も採り入れて受け入れ能力を拡大することを目指す方針だ。
ターミナルビルの拡張に際しては、南側臨時駐車スペースを転用し、ターミナルビルや駐機場の拡張に充てることを検討する。これにより減少する駐車スペースを補うため、第1・第2駐車場を立体駐車場として再整備する。ターミナルビルの拡張のみならず、駐機場の拡大や給油施設、給油体制、グランドハンドリング体制なども確保することを目指す方針だ。
取付誘導路については複線化して遅延を縮減することを目指す。現状、到着機が取付誘導路を使用して滑走路から駐機場に進入するため、出発機は接触防止のため、出発時刻になっても駐機場で待機することを余儀なくされるケースがある。そこで2本目の取付誘導路を整備することにより、出発機と到着機それぞれの動線を確保し、出発機は到着機に影響されることがなくなり、遅延を縮減することが可能になる計算だ。
加えて、1時間あたりの受け入れ便数増加に向けて、平行誘導路の整備も視野に入れる。現状、着陸機は滑走路端部のターニングパッドで折り返し、滑走路上を走行して駐機場に向かっており、滑走路を駐機場に向かって走行しているタイミングでは次の着陸機は着陸ができずに上空で待機することを余儀なくされている。
現在は1時間あたり2便程度の離着陸に留まっているが、今後、旺盛な需要に応じて1時間に8便以上の離発着を行うためには平行誘導路が必要だとし、将来の需要を見越して平行誘導路を整備することが必要とみている。平行誘導路を整備することにより、着陸機が平行誘導路に進入、滑走路上に障害物がなくなることから次の便が直ちに着陸可能となることで、1時間あたりに受け入れることができる便数の増加を実現していく。
平行誘導路整備については、1時間あたり8便以上が具現化してきた段階(1時間あたり6~7便程度)で、整備を進めていく構え。ただ、エプロン拡張および平行誘導路の一部整備作業と並行して、作業を前倒しで進めていくことも検討する。
今後の環境整備については、「空港の需要等を確認しながら、具体的に決めていくことになる」とコメントしつつ、「全て一度に進めるということはまだ現実的ではない。一方で、取付誘導路、あるいはターミナルビルの中のターンテーブルを含めた顧客の受入施設。こういうものは同時期に複数機が離着陸することを考えると、すぐにでも必要になってくる施設が出てくるのではないか。優先順位の高いものを決めて、路線拡大に合わせながら、今後、拡充していく」との見通しを示した。
ちなみに、取付誘導路に関しては、国土交通省が整備を進める事業になっており、今年度から予算化されている。その供用開始までには2年程度を要する見通しだ。
バスアクセス充実・強化
まちづくりと連携で賑わい創出
茨城空港のさらなるアクセス向上も推進する。「アクセスバスの充実や、多言語に対応した案内の充実、SNSによる交通情報の発信など、インバウンド旅客への情報発信も強化する」とし、バスアクセスの充実・強化を図るほか、情報発信にも努めていくとした。
まちづくりと茨城空港の連携も強化する。具体的には茨城空港と小美玉市の新しいまちづくりや、空のえき「そ・ら・ら」などとの連携を強化していく方針で、さらなる地域の賑わいを創出することを目指す。
ビジネス機需要取り込み、専用施設も視野
ビジネスジェットなど新たな需要の取り込みも進めていく。首都圏のビジネスジェット需要や富裕層向けの観光需要などを取り込むため、ビジネスジェットを活用したツアー造成や受け入れ環境の強化に取り組む考え。
ビジネスジェット需要の取り込みに向けて茨城県としては「需要が膨らんだ先にはそういう(ビジネスジェット専用の)施設を造るということも計画しなければいけないというふうに考えている」とのこと。「ビジョンでも、ある程度見越した上でのターミナルビルの大規模な建て替えみたいなことも含めているのではないかと、私は理解している」ことを明かし、ビジネスジェット専用の受け入れ施設の整備を検討していることを示唆した。
また、空港建築施設の省エネ化を推進し、空港分野における脱炭素化を促進するほか、災害時の対応能力の強化などにも取り組む方針だ。
※画像=茨城空港の将来ビジョンが策定。首都圏第3空港として飛躍の道筋を示した
https://jwing.net/w-daily/pict2025/2507/0707ibaraki-w.jpg