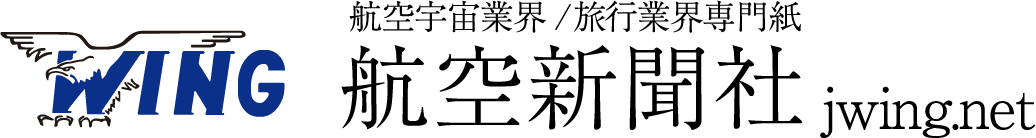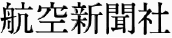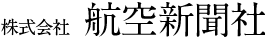ウイングトラベル特集
【潮流】世界からの評価に胸を張るために

サウジアラビア政府観光省が主導し、観光の未来の姿を創造する新たな枠組みの国際会議「TOURISE(トゥーライズ)」が11月11日から13日にかけて開催された。国際観光の未来像を考える新たな取り組みが始まる中で、「今」の観光を評価する「TOURISEアワード」の第1回目の受賞式が執り行われた。
その場で「最優秀観光地」として選ばれたのが東京だった。同アワードは、「現代の旅行者が求める意義深く、忘れがたい体験を提供する」点を審査対象として選定したという。
東京は最優秀観光地賞とあわせて「ベストフード&グルメ観光地賞」と「ベストエンターテインメント観光地賞」も受賞した。多様で質の高い日本の食文化や多彩なエンターテインメント体験を提供している点が特に高く評価された。加えて、来訪者が体験する全体的な質の高さと一貫性が認められ、満場一致で最優秀観光地賞を獲得することとなった。
サウジアラビアで東京が優秀な観光地として高評価を受けたのと時を同じくして、北欧のフィンランドでは、フィンランド旅行業協会(SMAL)主催の「フィンランド観光業表彰式2025」で日本が「2025年の海外旅行先大賞」を受賞した。
同賞は、フィンランドの旅行業界関係者・一般消費者1万2500人以上の評価を基に選定されるもの。日本は、四季の美しさ、伝統と未来が共存する独自性、多様な体験が得られること。そして高い安全性が評価されたのだという。
世界が日本の観光価値を高く評価しているのは誇らしい。しかし、手放しで喜んでよいかというと、必ずしもそうではない。なぜなら、日本人自身が多様な海外観光を体験する土壌が弱まりつつあるからだ。
昨年の訪日外国人旅行者と日本人出国者の比率は約4対1。訪日は過去最高を更新した一方で、日本人の海外旅行は依然として低迷している。このギャップは、観光立国を持続させるうえで看過できない。
背景には経済環境の変化がある。為替の影響や世界的な物価上昇により、特に長距離(ロングホール)の海外旅行の費用は1.6〜1.7倍にまで上昇した。旅行会社にとっては単価上昇による増収要因となるが、KNT-CTホールディングスの小山佳延社長が「危うい状況」と危機感を示すように、旅行需要が健全に回復しているとは言い難い。
一方で、世界の旅行者が日本を訪れる理由は決して「安いから」だけではないはずだ。
母国では得られない体験価値を求めて、費用に見合う、あるいはそれ以上の価値を日本に見出しているからこそ訪日が伸びている。ただ、今の日本では「高いから行けない」という議論に終始しがちだ。
異文化に触れ、国際感覚を養い、視野を広げる経験は、一個人にとっても、ひいては社会にとっても長期的な価値を生む。特に若い世代が海外で知見を広げることは、日本の将来の競争力を高める基盤となる。
観光業にとっても、日本人自身が世界の観光に詳しくなることは、インバウンド受け入れ力の向上に直結する。世界標準のサービスや価値観を知ることで、訪日観光の質もさらに高められる。
その意味で、「異文化交流」「国際的視野の獲得」「学術的スキルの向上」といった社会的意義が明確な海外経験に対しては、一定の公的支援を検討する余地があるだろう。
教育旅行や専門分野の研鑽を目的とした渡航、国際交流事業などは、費用面のハードルを下げれば参加層が広がり、長期的には国全体の力になる。海外旅行を“必要な人が確実に行ける仕組み”へと再設計する視点が求められている。
2026年度からスタートする「第5次観光立国推進基本計画」ではアウトバウンド促進が大きな柱となる見通しだ。同時に「日本人出国者に裨益すること」にも配慮した国際観光旅客税引き上げの議論も進む。これらの動きは、海外旅行振興でさらなる高みを目指す絶好のタイミングと言える。
世界を見ること、世界の観光を体験することは、日本の観光をより強くすることにつながる。その土壌を盤石なものにしていくことができれば、世界から寄せられる日本の観光に対する高い評価を胸を張って受け止めることができるのではないだろうか。(嶺井)