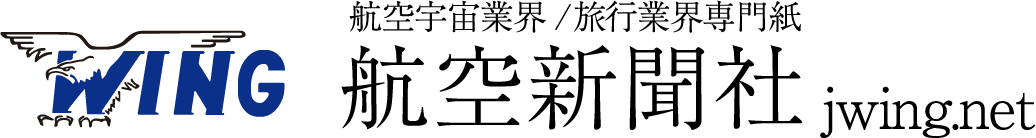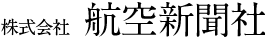ウイングトラベル特集
【本紙新年展望】持続可能な観光実現へ「真価」問われる2026年

旅行・観光の領域に「持続可能」というキーワードが登場して久しい。「サステナブル=持続可能」が声高に叫ばれる契機となったのは、2015年に国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)である。そのゴール地点として示された2030年は、当時は遠い未来のように受け止められていた。しかし今、その2030年を現実的な射程として捉え始める年こそが、2026年ではないだろうか。2030年という一つの到達点に向け、旅行・観光産業が「量の回復」から「質の持続」へと本当に転換できるのか。消費者マインドの多様化、国際情勢の不確実性が増す中で、2026年は旅行・観光に携わるすべてのプレーヤーにとって、まさに真価が問われる一年となる。
「第5次観光立国推進基本計画」が始動、日本の観光政策、成熟段階に踏み出せるか
2025年は、コロナ禍という言葉をほぼ完全に過去のものとし、世界の人々が再び「旅」へと大きく舵を切った年だった。日本においても、大阪・関西万博という世界的イベントを追い風に、訪日外国人旅行者数は11月時点で3900万人を突破。長らく目標として掲げてきた4000万人という数字が、現実のものとして目前に迫った。
一方で、その成果の裏側では課題も鮮明になった。特定地域への観光客集中による住民生活への影響、宿泊料金の高騰といったオーバーツーリズムの問題が顕在化し、円安や物価高の長期化は日本人の海外旅行マインドを冷え込ませた。訪日インバウンドの活況と、日本人旅行者の息苦しさ。このコントラストこそが、2025年の日本観光の実像であったと言える。
こうした状況を踏まえ、2026年は「第5次観光立国推進基本計画」が本格的に動き出す年となる。新たな計画が掲げるのは、観光客数の拡大そのものではなく、観光と地域住民の生活の質をいかに両立させるかという視点だ。これは、日本の観光政策が「成長」から「成熟」へと移行する意思表示でもある。
国際観光旅客税増額、その投資先がカギに
その実行を支える財源として、2026年7月から国際観光旅客税は現行の1000円から3000円へと引き上げられる。日本の観光振興策に充てられる財源が3倍になる意義は大きい。ただし重要なのは、財源の規模そのものではない。限られた観光地に人を集めるための投資なのか、それとも地域の受け入れ体制や人材育成、質の高い体験創出に振り向けられるのか。その使い道次第で、「持続可能」という言葉が空虚なスローガンに終わるか、実効性を伴う概念となるかが決まる。
観光立国を名乗る以上、訪日インバウンド一辺倒の成長はもはや許されない。国内旅行の活性化、日本人・外国人双方が納得して旅を楽しめる環境づくりが不可欠だ。その中で、観光庁や各地のDMOが単なる事業執行機関にとどまらず、地域の合意形成を主導し、観光の質を設計する存在として機能できるかどうかが試される。
日本人アウトバウンドは「分水嶺」の年、海外旅行市場は持続可能性を保てるか
日本人の海外旅行にとっても、2026年は分水嶺となる。円安や物価高が構造的な課題となる中で、海外旅行需要をどう掘り起こしていくのか。国際観光旅客税引き上げの一方で、長年要望されてきたパスポート取得費用の引き下げが現実のものとなったという話題は、アウトバウンド振興にとって明るい材料だ。しかし、仮に10年パスポートの取得費用が大幅に引き下げられたとしても、それが需要回復の決定打にならなければ、海外旅行市場の縮小という現実に直面することになる。政策に期待するだけではなく、業界自らが海外旅行の価値を再定義できるかが問われる局面だ。
デジタル技術の進化は旅行会社の存在意義を問い直す
さらに、旅行・観光を取り巻く環境はデジタル技術の進化によって急速に変化している。AIやDXの進展は、情報の非対称性を縮小させる一方で、旅行会社や観光事業者の存在意義を根本から問い直している。人手不足が深刻化する中で、単なる手配機能にとどまらない価値提案ができなければ、業界の持続性そのものが揺らぎかねない。
2030年というゴールを見据えたとき、問われているのは数値目標の達成ではない。観光が地域社会から信頼され、産業として誇りを持てる立ち位置を確立できるかどうかである。2026年は、その成否を分ける過渡期だ。政策の巧拙以上に、業界全体が変化を引き受ける覚悟を持てるかどうか――その一点に、日本の観光の未来がかかっている。(本紙編集長:嶺井政敏)